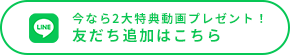営業クロージングのコツ|“断られない”ではなく“迷わせない”が正解
営業クロージングのコツ|“断られない”ではなく“迷わせない”が正解
多くの営業が「最後に押す」と考えがちですが、成否は初回接点の設計で8割決まります。水平思考でゴール(署名)から逆算し、途中の合意点を意図的に配置しておくと、最後は“確認作業”に変わる。これが営業クロージングの最短ルートです。
コツ① 事前合意のレールを敷く(ミニクロージング)
商談の各所で小さな“はい”を積み上げ、決定の摩擦を下げます。
- 合意の設計:「問題の定義 → 解決方針 → 評価基準 → 導入条件 → スケジュール」
- 確認フレーズ
- 「ここまでの整理でズレはありませんか?」
- 「評価は『コスト回収12か月以内・運用1人日以内』でよいですか?」
- 「承認プロセスは課長決裁→部長稟議で合っていますか?期限は○月○日ですね」
この“合意ログ”が最後の意思決定の根拠になります。
コツ② 判断材料を可視化する(迷いの源を断つ)
人は比較不能だと保留します。保留=失注。三点セットで“比べられる状態”を作る。
- 1枚ROI:投資額・削減/増収・回収期間・感度(±20%)
- リスクの先出し:想定トラブルと回避策(担当/期限/エスカレーション)
- 第三者の証拠:事例、数値、評価コメント(同業×導入前後の差)
例)「初期80万円・運用月3万円、平均で12か月回収。既存A社は問合せ+32%、人的ミス-41%。想定リスクは運用定着、初月は週1の伴走で吸収。」
コツ③ 迷いを刈り取る言葉(倫理的テクニック)
押し切らず、意思決定を支援する言い回しに置き換えます。
- 推定承諾:「では、評価基準を満たした場合は○日着手で進めますね」
- 二者択一:「A:初期コストを下げてゆるやかに開始/B:成果優先で並走を厚く。どちらが御社向きですか?」
- 理由付き期限:「制作枠が月3社まで。○日までに確定で初回キックオフが○/○可能です」
反論対応テンプレ(3大論点)
1)価格が高い
- 「高い」の定義を合わせる → 「12か月回収を前提に費用対効果で見ていただけますか?」
- 代替案提示 → 「初期を下げ、成果報酬を厚くする設計も可能です」
2)他社比較中
- 軸を設計 → 「評価基準(機能/運用負荷/回収期間/伴走)で並べるとどう見えますか?」
- 差別化の事実 → 「伴走週1×4週は当社固有。定着率92%の源泉です」
3)社内稟議が重い
- 稟議用1枚資料を提供 → 「要点(目的/費用/効果/リスク/スケジュール)の骨子をこちらで作ります」
- 期限コミット → 「稟議提出が○日、決裁見込みが○日。差し障りあれば私が説明会に同席します」
そのまま使えるクロージング・スクリプト
「評価基準(回収12か月/運用1人日以内)は満たせています。リスクは初月の定着ですが、週1伴走で管理します。制作枠の都合で、進めるなら○/○開始が最短です。
進め方は二択です。A:初期費用抑制プラン/B:成果最優先伴走プラン。どちらが御社に適しますか?」
“はい/いいえ”で詰めず、A or Bで前に進めるのがポイント。
運用KPIとマネジメント
- 一次KPI:案件ごとの“ミニ合意数”、稟議通過率、提案→決裁までの滞留日数
- 二次KPI:成約率、平均回収期間、導入後の定着率
- レビュー:失注理由を**「情報不足・合意不足・証拠不足・タイミング」**に分類し、次回の“合意ポイント”へ還元
実績・権威性の裏付け(ポリシー)
本記事の型は、BtoB/BtoC双方のコンサル現場で二桁%の成約率改善が続く再現性の高い手法から抽出しています。SPIN質問法、Cialdiniの説得原理、意思決定理論(損失回避・選択肢設計)を実務へ翻訳し、**「迷わせない設計」**に統合しています。
まとめ
営業のクロージングはテクニックより設計です。
- 事前合意でレールを敷く、2) 判断材料を1枚で可視化、3) 迷いを刈る言葉で意思決定を支援。
この3点を徹底すれば、クロージングは“押す”から“確認”に変わります。